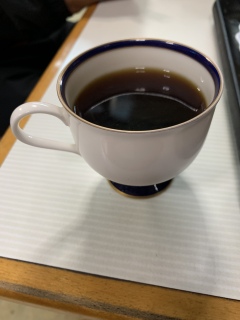039:オムライス
どうということのない、白いマグカップが一人に一個。西暦21XX年、全世界で食器はそれに限られていた。
食糧危機ではない。むしろ食べるものは質・量・種類ともに史上空前の規模を誇り、全人類は健康に、幸福に食文化を謳歌していた。全てマグカップのおかげである。
もちろん前世紀までのアナログマグカップとはわけが違う。
本体の側面がタッチパネルになっており、飲みたい/食べたいものを自由に検索できる。コーヒーひとつとってさえ、産地も濃さもブレンド具合もお好み次第。食べ物も白米、ラーメン、シリアル、オムライス、カオマンガイなどなど古今東西何でもござれで、刺身やフルーツなどという生ものも可能。メニューを決められない時も、持ち手のセンサーで持ち主の体調や感情が読み取られ、最適なおすすめメニューがタッチパネルに表示される。欲しいものを決定したら、側面を底から指でスワイプし、好きな高さまでマークして、量を決める。ここまで確定すると、オンライン上から食品データがダウンロードされるので、あとは至る所にあるフードスポットに行き、食品生成マシンにマグカップを置けば、目当てのご馳走がカップの中に満たされるという寸法。
つまり合成食品だが、見た目や味、食感は完璧に再現され、ついでに持ち手のセンサーで読まれた情報にそって、味や栄養が持ち主に最適化されている。まずいわけがないし、体にも申し分ない。ちなみに、食品生成のための原材料は海水、土、石、空気など。その辺にあるものを食品生成マシンに入れれば、分子レベルで分解して好きに再合成してくれる手軽さである。
ということで、このマグカップシステムは、発表直後から基礎インフラとみなされた。国連の強力な後押しもあってわずか数年で全世界に行き渡り、従来の食糧事情をがらりと変えてしまった。もちろん一次産業はほぼ駆逐され、当初はこれまでの「自然食」消滅を嘆く声もあったが、結局は「誰もが食べていける」とあって、反対派もそのうち矛を収め、マグカップで和解の盃となった。かくて人類の辞書から飢餓の文字がなくなり、ダウンロード可能な食品データは日々増え続け、世界はいにしえの人々が夢見た黄金時代のただ中にある。
かく言う僕は、そのマグカップシステムの会社に勤めている。
今は、夜の食品データセンターの作業室だ。同僚は少し前に帰り、周囲ではサーバーが低くうなるばかり。
マグカップの中身をスプーンで口に運んだ。ねっちょりした魚団子の食感。僕の舌にはなじんだ味だが、正解かどうかは分からない。父方のおじいちゃんの故郷の魚料理だという。
おじいちゃんは南太平洋の出身だけれど、温暖化で島が沈み始め、僕が生まれるずっと前に全ての島民が退去させられた。僕は物心ついてからずっと、帰りたい帰りたいというおじいちゃんを見てきたから、島が小さな岩になって、それでもまだ海面に出ていた数年前、旧住民向けの現地ツアーにおじいちゃんを連れていこうとした。けれど出発直前の巨大台風で、その小さな岩は跡形もなく沈んだ。おじいちゃんはすっかり気落ちして、その年のうちに亡くなった。
僕がこの魚団子の食品データを完成させたのはついさっきだ。というより、もともと作ったまま放置していたデータを、ようやくアップロード用に微調整した。
おじいちゃんはこの食品データの味を認めようとしなかった。何回作り直しても、悲しそうに首を横に振った。
――あの島では魚はもっと美味しい。潮風や波の光、足の裏の砂のざらざら、そんなものがみんな味になる。材料がそっくり同じでも、これを再現はできないだろう? 何より、食器だよ。このお団子は、いい香りの葉っぱで包んで蒸さなくては……。
その葉っぱのとれる木は、一本残らず沈んでしまった。他の土地に移しても育たなかったのだ。つるつるのマグカップの中の魚団子のデータは、葉っぱの香りなど一すじも知らない。
僕は魚団子を平らげ、マグカップをひっくり返した。
この時代のスマホといえば、実はこのマグカップだ。底面がディスプレイになっていて、中身が入ったままでは見られない仕掛けなのだ。食事中は食べ物や会話を楽しみましょう、というわけだ。
ディスプレイには生中継が表示されている。主要国の偉い人々の会合だ。
『希少な料理のデータ化をさらに推し進めるのです……少数民族の料理を採集し、古代のレシピを再現し……』
さらに、それらを有料配信すれば、巨大産業となる。偉い人々と一緒に映っているのは、うちの社長だ。当然だ、晩餐に使うのはうちのマグカップなのだから。
『この食の黄金時代はさらに発展します……古今東西、あらゆる料理を皆様の口にお届けできるでしょう……』
でも、その中におじいちゃんの魚団子は永遠にない。
僕は深呼吸し、会合出席者全員のマグカップに社員IDで違法アクセスした。それらに入っていたご馳走のデータの数々を、みんな魚団子のデータで上書きしてやる。
そして、全員のマグカップの底のディスプレイに宛てて、ひとつメッセージを送った。
〈この料理の本当の味を教えてくれるまで、皆さんの大好物のレシピデータを消し続けます〉
(了)
食糧危機ではない。むしろ食べるものは質・量・種類ともに史上空前の規模を誇り、全人類は健康に、幸福に食文化を謳歌していた。全てマグカップのおかげである。
もちろん前世紀までのアナログマグカップとはわけが違う。
本体の側面がタッチパネルになっており、飲みたい/食べたいものを自由に検索できる。コーヒーひとつとってさえ、産地も濃さもブレンド具合もお好み次第。食べ物も白米、ラーメン、シリアル、オムライス、カオマンガイなどなど古今東西何でもござれで、刺身やフルーツなどという生ものも可能。メニューを決められない時も、持ち手のセンサーで持ち主の体調や感情が読み取られ、最適なおすすめメニューがタッチパネルに表示される。欲しいものを決定したら、側面を底から指でスワイプし、好きな高さまでマークして、量を決める。ここまで確定すると、オンライン上から食品データがダウンロードされるので、あとは至る所にあるフードスポットに行き、食品生成マシンにマグカップを置けば、目当てのご馳走がカップの中に満たされるという寸法。
つまり合成食品だが、見た目や味、食感は完璧に再現され、ついでに持ち手のセンサーで読まれた情報にそって、味や栄養が持ち主に最適化されている。まずいわけがないし、体にも申し分ない。ちなみに、食品生成のための原材料は海水、土、石、空気など。その辺にあるものを食品生成マシンに入れれば、分子レベルで分解して好きに再合成してくれる手軽さである。
ということで、このマグカップシステムは、発表直後から基礎インフラとみなされた。国連の強力な後押しもあってわずか数年で全世界に行き渡り、従来の食糧事情をがらりと変えてしまった。もちろん一次産業はほぼ駆逐され、当初はこれまでの「自然食」消滅を嘆く声もあったが、結局は「誰もが食べていける」とあって、反対派もそのうち矛を収め、マグカップで和解の盃となった。かくて人類の辞書から飢餓の文字がなくなり、ダウンロード可能な食品データは日々増え続け、世界はいにしえの人々が夢見た黄金時代のただ中にある。
かく言う僕は、そのマグカップシステムの会社に勤めている。
今は、夜の食品データセンターの作業室だ。同僚は少し前に帰り、周囲ではサーバーが低くうなるばかり。
マグカップの中身をスプーンで口に運んだ。ねっちょりした魚団子の食感。僕の舌にはなじんだ味だが、正解かどうかは分からない。父方のおじいちゃんの故郷の魚料理だという。
おじいちゃんは南太平洋の出身だけれど、温暖化で島が沈み始め、僕が生まれるずっと前に全ての島民が退去させられた。僕は物心ついてからずっと、帰りたい帰りたいというおじいちゃんを見てきたから、島が小さな岩になって、それでもまだ海面に出ていた数年前、旧住民向けの現地ツアーにおじいちゃんを連れていこうとした。けれど出発直前の巨大台風で、その小さな岩は跡形もなく沈んだ。おじいちゃんはすっかり気落ちして、その年のうちに亡くなった。
僕がこの魚団子の食品データを完成させたのはついさっきだ。というより、もともと作ったまま放置していたデータを、ようやくアップロード用に微調整した。
おじいちゃんはこの食品データの味を認めようとしなかった。何回作り直しても、悲しそうに首を横に振った。
――あの島では魚はもっと美味しい。潮風や波の光、足の裏の砂のざらざら、そんなものがみんな味になる。材料がそっくり同じでも、これを再現はできないだろう? 何より、食器だよ。このお団子は、いい香りの葉っぱで包んで蒸さなくては……。
その葉っぱのとれる木は、一本残らず沈んでしまった。他の土地に移しても育たなかったのだ。つるつるのマグカップの中の魚団子のデータは、葉っぱの香りなど一すじも知らない。
僕は魚団子を平らげ、マグカップをひっくり返した。
この時代のスマホといえば、実はこのマグカップだ。底面がディスプレイになっていて、中身が入ったままでは見られない仕掛けなのだ。食事中は食べ物や会話を楽しみましょう、というわけだ。
ディスプレイには生中継が表示されている。主要国の偉い人々の会合だ。
『希少な料理のデータ化をさらに推し進めるのです……少数民族の料理を採集し、古代のレシピを再現し……』
さらに、それらを有料配信すれば、巨大産業となる。偉い人々と一緒に映っているのは、うちの社長だ。当然だ、晩餐に使うのはうちのマグカップなのだから。
『この食の黄金時代はさらに発展します……古今東西、あらゆる料理を皆様の口にお届けできるでしょう……』
でも、その中におじいちゃんの魚団子は永遠にない。
僕は深呼吸し、会合出席者全員のマグカップに社員IDで違法アクセスした。それらに入っていたご馳走のデータの数々を、みんな魚団子のデータで上書きしてやる。
そして、全員のマグカップの底のディスプレイに宛てて、ひとつメッセージを送った。
〈この料理の本当の味を教えてくれるまで、皆さんの大好物のレシピデータを消し続けます〉
(了)